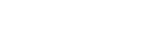先日、佐藤可士和さんの講演会に行ってきました。
可士和さんが提唱するデザインの哲学は、一言で言うと「定義をぶっ壊す」ことにあります。それは単なるデザインの枠を超え、社会課題へのアプローチとしても革新的です。従来の価値観や序列を解体し、上や下、強者や弱者といった概念そのものを揺るがすことで、平等な世界を創り出す。このような視点から生まれるデザインには、既存の枠にとらわれない可能性が秘められています。

物流施設「ALFALINK相模原」は、その好例です。この施設は単にモノを運ぶ場としてではなく、地域社会との接点を持つ「開かれた物流施設」として設計されています。一般市民が利用できるイベントスペースやスポーツコートを施設の中心に配置することで、物流の仕組みを自然に目にする機会を提供しています。従来の「見学ツアー」のように興味のある人だけが足を運ぶのではなく、日常生活の中で物流という存在を感じ取れる設計になっているのです。
このアプローチの面白さは、「意味づけをしない」ことにあります。用意された「これはこういうものだ」という意図が透けて見えると、人はそこに上下関係や押し付けを感じ、距離を置いてしまうことがあります。しかし、意味づけを最小限に抑え、余白を残すことで、そこに自由な解釈や新たな価値が生まれる可能性を開くのです。この「余白」があるからこそ、地域住民が自然に物流の存在を受け入れ、競合企業同士が協業する場が生まれています。

さらに、この考え方は物流施設に限らず、あらゆる分野で応用可能です。例えば、ハラール食品のビジネスにおいても同じことが言えます。通常、ハラール食品はイスラム教徒をターゲットにしているとされますが、それを「宗教の壁を超えた美食の提案」と捉え直せば、ターゲットは宗教に限定されず、「日本の多様な味を楽しむ」新しい価値を生み出すことができます。このような意味変換は、商品やサービスの可能性を広げ、より多くの人々に受け入れられるきっかけとなるでしょう。
可士和さんの哲学が教えてくれるのは、デザインやビジネスにおいて「定義に縛られない」重要性です。ガチガチに意味づけをしないことで、予期しない可能性が生まれる。その余白こそが、新しい価値の発生を促すのです。そして、上や下、強者や弱者といった概念を壊し、フラットな場を創り出すことが、社会課題の解決にもつながります。この視点は、物流施設や商品開発に限らず、私たちの日常にも多くの示唆を与えてくれるのではないでしょうか。